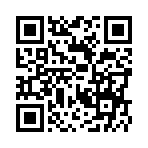グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2011年05月03日
火鉢。
ここ数日、火鉢を点けています。
春なのに・・・という感じもしますが。。

朝晩はけっこう冷えるので。。
外は日が当たるとあたたかいけれど、
家の中はまだまだ肌寒いです。
なので、お願いして、火鉢を稼動してもらいました。
実はこの火鉢に火を入れたところを見るのは、私は初めてです。
この火鉢、何年か前に、たけちゃんが一目ぼれして思わず買ってしまった火鉢です。
ほしい!と思って買おうとしたけど、手元にお金がなくて、
「これ、買うのでとっておいてください!!」
と叫んで、慌てて銀行に行ってお金おろして、やっとこさ手に入れた、
思い出の火鉢なんだそうです(笑)。
にもかかわらず、
寒い寒い冬も一切使われず、ずっとほこりをかぶっていました。
でも、最近やっといろいろが片付いてきて、火鉢の置き場所もできたので、
火を入れることにしました。
「そんなにあったかくはならないよ」
と言われていて、そんなに期待もしていなかったのだけど、
ムードというか、なんというか、そういう意味での期待はしつつ。。
実際に火を入れてみて、確かにストーブのような暖かさはないのだけれど、
あるだけで空気が和らぐというか、火がともる感じがとてもいいと思いました。
手をかざすと、じんわりとあたたかい。。
ふと思い出して、久しぶりに一冊の本を取り出しました。
『建築は詩』。
吉村順三という建築家の言葉を集めた本です。
以前、奈良に住む友達に連れられて京都へ行った際に、
ステキな本屋さんで出会った、思い出の本です。
気に入って、何度も何度も読みました。
確か、その中に、家の中に”火”があるといい、みたいなことが書いてあったような。。
パラパラとページをめくると。
「僕は住宅ではリビングというより、食事をする場所がいちばん中心と思うんです。
家族みんなでそろって食事をすること、これがとても大事じゃないか」(家のセンター)
とか、
「必ず主婦の居られるコーナーを作っているつもりです。
主婦が幸福でなければ、いい家庭にならないし、家もよくはならないですね」(主婦のコーナー)
とか、
「人間は非常に水と関係があるんじゃないでしょうか。
それから、もうひとつ、火ですよ」(水と火)
「水というものは、人間の幸福に関係があるということです。
それから光ね。
火というのは、誰でも火を持つことをやってみたら皆好きになりますね。
これは昔から人間の身体の中にある本能でしょう。1つの。
実際に火を炊いて話をしていると全然、雰囲気が楽しくなってきます」(光と火)
確かに。
火を前にすると、穏やかで、楽しい気持ちになってきます。
私は建築に対する造詣はなく、
吉村順三という建築家との接点はこの本以外にないのですが、
この本の冒頭で、
「建築家として、もっとも、うれしいときは、
建築ができ、そこへ人が入って、そこでいい生活がおこなわれているのを見ることである。
日暮れ時、一軒の家の前を通ったとき、家の中に明るい灯がついて、
一家の楽しそうな生活が感ぜられるとしたら、それが建築家にとって、
もっともうれしいときなのではあるまいか」
と書かれていたのを見て、この建築家に惹かれてしまいました。
そもそも、「建築は詩である」って言っちゃうところがいいなぁと。。
そして、吉村氏が、生前、”これからの建築家のあり方”を問われたとき、
「簡素でありながら美しいもの、自分たちの住んでいる日本の、
長年にわたる風土と文化によって培われてきたさまざまな建築から学び、
日本の気持ちから出たものをつくるべきでしょう」
と語ったそうで、共感というとおこがましいのですが、それに近い感情を覚えました。
そして、この考え方は、建築にとどまらないと思いました。
この火鉢の五徳の上にやかんをのせておきました。
しばらくして、湯のみに注いで飲んでみると、お湯がやわらかい!
「お湯がやわらかい」ってこういうことを言うんだ~と、2人で感動しました(笑)。
ちなみに、本からの文章は、私の主観的な抜粋なので、
ちゃんと読んでみたい方は、原本にあたってください。
春なのに・・・という感じもしますが。。

朝晩はけっこう冷えるので。。
外は日が当たるとあたたかいけれど、
家の中はまだまだ肌寒いです。
なので、お願いして、火鉢を稼動してもらいました。
実はこの火鉢に火を入れたところを見るのは、私は初めてです。
この火鉢、何年か前に、たけちゃんが一目ぼれして思わず買ってしまった火鉢です。
ほしい!と思って買おうとしたけど、手元にお金がなくて、
「これ、買うのでとっておいてください!!」
と叫んで、慌てて銀行に行ってお金おろして、やっとこさ手に入れた、
思い出の火鉢なんだそうです(笑)。
にもかかわらず、
寒い寒い冬も一切使われず、ずっとほこりをかぶっていました。
でも、最近やっといろいろが片付いてきて、火鉢の置き場所もできたので、
火を入れることにしました。
「そんなにあったかくはならないよ」
と言われていて、そんなに期待もしていなかったのだけど、
ムードというか、なんというか、そういう意味での期待はしつつ。。
実際に火を入れてみて、確かにストーブのような暖かさはないのだけれど、
あるだけで空気が和らぐというか、火がともる感じがとてもいいと思いました。
手をかざすと、じんわりとあたたかい。。
ふと思い出して、久しぶりに一冊の本を取り出しました。
『建築は詩』。
吉村順三という建築家の言葉を集めた本です。
以前、奈良に住む友達に連れられて京都へ行った際に、
ステキな本屋さんで出会った、思い出の本です。
気に入って、何度も何度も読みました。
確か、その中に、家の中に”火”があるといい、みたいなことが書いてあったような。。
パラパラとページをめくると。
「僕は住宅ではリビングというより、食事をする場所がいちばん中心と思うんです。
家族みんなでそろって食事をすること、これがとても大事じゃないか」(家のセンター)
とか、
「必ず主婦の居られるコーナーを作っているつもりです。
主婦が幸福でなければ、いい家庭にならないし、家もよくはならないですね」(主婦のコーナー)
とか、
「人間は非常に水と関係があるんじゃないでしょうか。
それから、もうひとつ、火ですよ」(水と火)
「水というものは、人間の幸福に関係があるということです。
それから光ね。
火というのは、誰でも火を持つことをやってみたら皆好きになりますね。
これは昔から人間の身体の中にある本能でしょう。1つの。
実際に火を炊いて話をしていると全然、雰囲気が楽しくなってきます」(光と火)
確かに。
火を前にすると、穏やかで、楽しい気持ちになってきます。
私は建築に対する造詣はなく、
吉村順三という建築家との接点はこの本以外にないのですが、
この本の冒頭で、
「建築家として、もっとも、うれしいときは、
建築ができ、そこへ人が入って、そこでいい生活がおこなわれているのを見ることである。
日暮れ時、一軒の家の前を通ったとき、家の中に明るい灯がついて、
一家の楽しそうな生活が感ぜられるとしたら、それが建築家にとって、
もっともうれしいときなのではあるまいか」
と書かれていたのを見て、この建築家に惹かれてしまいました。
そもそも、「建築は詩である」って言っちゃうところがいいなぁと。。
そして、吉村氏が、生前、”これからの建築家のあり方”を問われたとき、
「簡素でありながら美しいもの、自分たちの住んでいる日本の、
長年にわたる風土と文化によって培われてきたさまざまな建築から学び、
日本の気持ちから出たものをつくるべきでしょう」
と語ったそうで、共感というとおこがましいのですが、それに近い感情を覚えました。
そして、この考え方は、建築にとどまらないと思いました。
この火鉢の五徳の上にやかんをのせておきました。
しばらくして、湯のみに注いで飲んでみると、お湯がやわらかい!
「お湯がやわらかい」ってこういうことを言うんだ~と、2人で感動しました(笑)。
ちなみに、本からの文章は、私の主観的な抜粋なので、
ちゃんと読んでみたい方は、原本にあたってください。